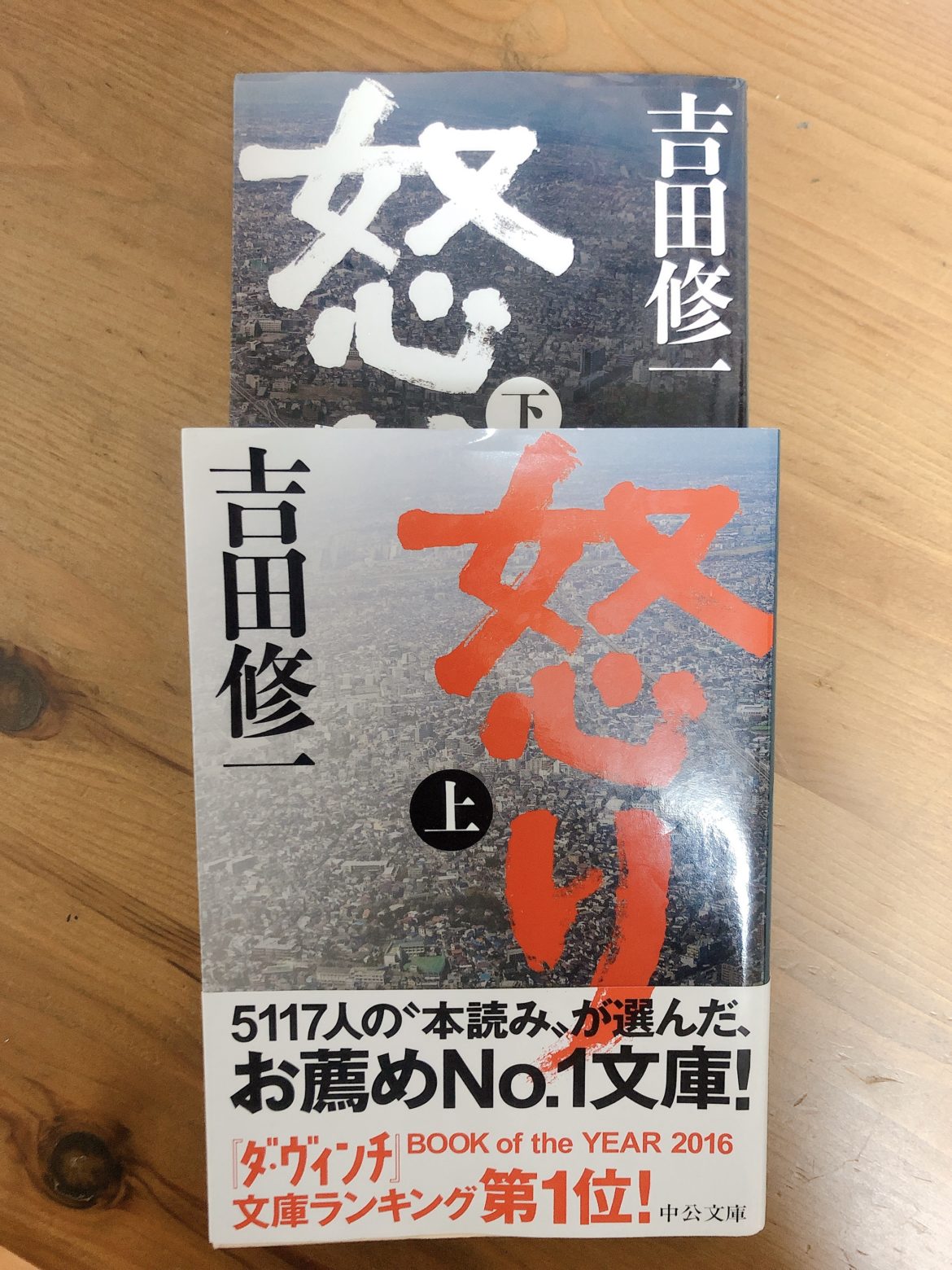吉田修一ファンとして、書かずにいることをモヤモヤしてるほどだったので、今回は『怒り』について。
まず、小説を読みました。
上下巻、たっぷり時間をかけて読みました。
それから映画を観ました。
正直、結論から言ってしまうと、映画は期待外れだったし、原作が素晴らしいだけに、納得のいく出来ではなかった。
キャストの演技は置いておいて、小説で語られる大事な部分、核の部分に触れていないような気がして、観終わった後しばらくは「うーん」と唸ってしまったし、たまたま隣で一緒に観ていた母に、「違うんだよ、そうじゃないのよ」と力説してしまったほど。(母は原作は読んでいない)
正直、このモヤモヤとした感情をうまく表せるかも自信がないけれど、もう一度小説を読み直したので、感想を書き残しておきたいと思います。
※ここからネタバレを含みます
あらすじ
大筋としては、三人の若い男にスポットライトが当たる。
・千葉県の漁協で働きながら上司の娘と付き合う、素性の分からない男。
・沖縄の離島で野宿をしながら、時々日雇いとして働く、素性の分からない男。
・新宿の発展場で知り合った、ゲイの会社員の家に住み着く、素性の分からない男。
警察が追うのは、東京八王子に住む夫婦を惨殺し、その家の壁に『怒』という血文字を残して逃亡中の男。
この犯人の特徴が、三人の男を取り巻く人々を惑わす。それぞれに事情を抱えた人間が、疑り、信じ、祈り、絶望し、また祈りを繰り返す。小説でも映画でも、後半になるまで犯人は分からない。共通点を見つけ、怪しいと感じさせるのは三人とも。ストーリーの中の登場人物と同じ、読んでいる(観ている)こちらも一度疑い出したら、もう何が本当か分からなくなってくる。
小説と映画の怒りの違い

映画において私が残念だなと感じたのは、映画が伝えてくる『怒り』が、私たちの想像する怒りそのものに見えるのに反して、原作で問われる『怒り』は、もっと別のもののような気がするから。
結局、犯人は事件とは無関係のところで刺殺されるはめになり、刑事の北見と南條は、長い間追いかけてきた犯人の山神を、あと寸前のところで死なせることになってしまう。
時々現れる事件後の山神と接触した人間や、その前に付き合いのあった女からの話で、彼の人となりは語られる場面もあるが、どうして惨殺な殺人事件を起こしたのか、そこに不気味な文字を残した意味などは迷宮入りのまま事件は終わりを告げる。
正直、「なんで?」と答えを知りたくなるのは避けられない。
事件の真相を知りたいのは、フィクションノンフィクション関わらず読者なら当たり前だと思う。
でもこの小説においては、もっと違う部分に重きを置いて物語が進んでいることに途中から気付く。
素性の知れない男たちを愛した人間が、そこにちゃんと存在するからだ。
目の前にいる人間を信用できないと思いながら、愛するとはどういう感覚だろうと思う。また、愛する人間を信じようとして、出来ない自分に気付いた時の絶望はどんなものだろうと想像する。
多くのレビューを読むと書かれているように、吉田修一さんは、社会における弱者を書くのを得意としてるよう。『横道世之介』なんかはそういった分かりやすい弱者のいない爽やかなものだけど、ヒット作の『悪人』や『パレード』などにも今回の『怒り』に通ずる人物が出てくる。
その社会的に弱いと人物自身が感じている部分が、相手を信用するということにおいて邪魔をしてくるのが悲しい。本編にも出てくる通り、信じられないのは相手ではなく、自分自身なのかもしれないと疑いの矢印がひっくり返るからである。
登場人物ほとんどが弱々しくてめめっちくて、あーもう!とイライラする部分も少なからずあるのだが、でも本来、生きるということは、そういうカッコ悪いことの連続かもしれないなと思う。
我が子や恋人を大事に思えば思うほど、真正面からぶつかるのが怖くなり、出てくる言葉が嘘っぽくなる。
特に洋平と愛子の親子間にある、ギクシャクした愛情表現なんかは、日本における父娘のリアルなイメージかも知れない。
話は逸れてしまったけれど、小説でみえてくる『怒り』は、愛子が恋人の田代を信じてやれなかった怒り、裏切った怒り、優馬が直人を最後までよそ者にしてしまった怒り、何も見ようとしていなかった怒り。
映画で見えてくる『怒り』は、犯人役の森山未来が喚き散らす狂気の怒り、大事なものを傷つけられた辰哉の怒り。
個人としては、結末に納得がいったので(ここは賛否両論。最悪な終わり方と書いてる人もいた)、映画でも是非そこへ向かっていってほしかったのだけれど、森山未来の演技力に責任を負わせ過ぎではないのかっていう脚本が残念だった。
後から色々読んだら映画も最初は4時間あったみたい。それを二時間とちょっとに縮めたっていうから、そうなる前の映画を観てみたい気がする。
色々読んでるうちに出てきたライターのレビューにも書いてあった、「愛する人間を守りたいと思う気持ち」のあまり、起こっていく出来事が映画は省かれている印象が強くて非常に残念。
どうしてそうなったか、どうしてそうしなければならなかったのかという経緯が(猟奇殺人の動機は別)原作は懇切丁寧に書かれているのに対して、映画は何の説明もない。個人的には非常に残念。
動機について
正直これについては、原作でも全く明らかになっていないので、ミステリー小説としては物足りなさを感じる人が多いのかもしれない。でも読み進めているうちに、それぞれの人物に感情移入していくので、犯人山神の不可解な行動には、もともと何かが欠落しているサイコパスであったというのが正解で、彼のやることに意味を見出したら、それこそこちらがおかしくなるという気持ちに変化していった。
作者ももしかしたら、初めと終わりで書きたいことが変わっていったのかもと思う。
本筋とは無縁に思える描写
吉田修一さんの作品の好きな部分は、大きな話の展開には関係のないエピソードが妙に頭に残ったり、グッと感情移入させる効果を持つところ。
例えば、
ゲイである優馬が、兄と二人、女でひとつで母に育ててもらったこと。新聞配達を小学生から中学生まで続けたこと。周りには不幸な少年に見られたかも知れないが、本人はとても幸せだったこと。それを直人が羨ましいと言ってくれたこと。
優馬が同僚の持っているバッグを通りすがりに褒めるところからは、誰でも真似できるようなものでない明るさと優しさを持ち合わせた人間であることが伝わる。
従姉妹の明日香が夫を亡くして、無意識のうちに海に入っていく部分には、それを必死で追いかける愛子が出てくる。一見、頭の弱い残念な存在に映る彼女が、本当は何が正しいのか教えてくれる女性なのだとわかると、不思議とあったかい包容力さえ感じる。
「宅配ピザの中身の少ないサラダ」とか。リアルに映像が浮かんでくる描写が、私は好きだ。
実在のアーティスト名などが使用されていることで、陳腐な印象を受けるとレビューに書いてる人もいたのだけれど、私はそこもリアリティがあって好きだった。
舞台となる街についても丁寧に書かれているので、その土地の空気感に浸ることができる。
千葉も東京も沖縄も、実際に行ってみれば、吉田修一が書いた場所があるわけで、実際に現地に行けば、登場人物たちが生きているのではと探したくなってしまうと思う。
実在の団体名や呼称を使うのは、そういった意味でも効果的かなと思った。
ラストは・・
辰哉のあまりにも唐突な行動には唖然とさせられるけれど、それが山神の犯した事件の運命だったとも言えると私は思う。泉が刑事に真実を話しに行ったことで救われた気持ちがした。あれがなかったらもっとモヤモヤしたと思う。
映画と小説では、ラストの描き方がずいぶんと違うので、好き嫌いは置いておいてどちらも楽しめると思う。森山未來の役への入り込みは凄かったし。
ただ映画「怒り」においてベストアクト賞をあげるとなると、高畑充希ちゃんかなと。
ほんの少ししか登場しないけれど、あの間と声のボリューム、息を止めて見入ってしまった。あんな演技ができる人だとは知らなくて驚いた。
また吉田修一×妻夫木聡が見たい。